
日本ナレッジ・マネジメント学会アート部会
第27回KMSJアート部会研究報告書
【日時】平成25年2月16日(土)17時〜20時
【場所】小石川後楽園涵徳亭日本間(JR飯田橋5分)
【テーマ】日本経営思想の原点を辿る(その2)〜渡辺崋山の経営哲学
【参考資料】
(1)鎌田道隆著「渡辺崋山 洋学開花期の芸術を思想」(平凡社)
(2)蔵原惟人著「渡辺崋山 思想と芸術」(新日本出版)
(3)小川晴久著「実心実学の発見」(論創社)
(4)芳賀登著「士魂の人 渡辺崋山探訪」(つくばね舎)
(5)佐藤昌介著「渡辺崋山」(吉川弘文館)
(6)ドナルド・キーン著「渡辺崋山」(新潮社)
【小野瀬由一発表概要】
1.崋山の芸術と思想
1)崋山の芸術
・十代⇒
12歳の事件:日本橋付近で備前候の先供に当たって打擲(ちょうちゃく)を受け発憤し、
儒者になろうと決意し儒学者鷹見星皐の一門佐藤一斎につい
て学ぶが、
数年後に差し迫った生活のため放棄。
16歳画家志す:幼い頃から絵心あり、鷹見星皐の紹介により町絵師白川芝山に入門。
芝山は華山の付け届けが少ないとして翌年崋山を破門。
翌年、江戸画壇(文人画)谷文晁の門人金子金陵に師事し、その後金陵の紹介で谷文晁に師事。
同門には後に華山に師事した椿椿山がいた。
・二十代⇒
20歳の頃:初午灯籠の灯籠画を描いて内職とした。百枚がわずか一貫文。
26歳『一掃百態』:序文(東洋画論の伝統を踏まえた勧善懲悪的な風俗画の有り方)+鎌倉から江戸中期までの古風俗模写図(40頁)+十九世紀初頭江戸風俗図(41頁)からなる一冊。
 | 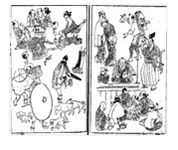 | 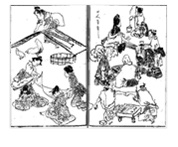 | 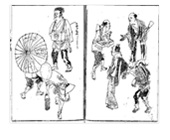 |
・三十代⇒
31歳:文政六年(1823)幼児から御伽役を命じられた藩主三宅康和を失い、田原藩士和田伝の娘たか(17歳)を嫁にする。
32歳:父親貞道 が死し遺禄80石継ぐ。翌日、崋山の主治医兼蘭学の師匠吉田長淑が死す
33歳:「華山」を「崋山」と改める。風景画集『四州真景』まとめる。
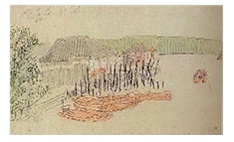 | 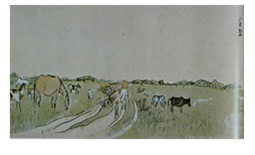 |  |
・四十代⇒『校書(げいしゃ)図』、『鷹見泉石像』(国宝)、『黄粱一炊図』

2)崋山の藩政経営思想
・文政十年(1827):崋山35歳のとき、田原藩主十三代三宅康明が没し、世子であった三宅友信を廃して、姫路城藩主酒 井雅楽頭(うたのかみ)忠実の第六子を三宅家の養子に迎え、十四代康直として藩主就任。三宅友信を推した崋山は一旦挫折したが、康直の世子に友信の長子を 立てて三宅家の血統をつなぐことに献策し成功した。
・文政十二年(1829):崋山37歳のとき、江戸定府藩士の教育稽古所が設けられその所長に就任。
・天保三年(1832):崋山40歳のとき、田原藩年寄職として家老に抜擢され、百石の禄米と二十石の役料の大身に出世。
・天保四年(1833):崋山41歳のとき、天候異変のため田原視察に洋式兵学者鈴木春山を同行。同年七月紀州商船田原領内で遭難し、漂着した荷物を領民 が隠ぺいしたことから補償問題が発生し崋山の奔走により少額賠償金で落着。同時期、幕府から新田開発の命があり開墾中止を画策し翌天保五年に廃案に成功。 同年十二月藩政の改革のため新俸禄体系「格高分合制」すなわち職務により増禄を行う制度を導入した。
・天保五年(1834):崋山42歳のとき、天保飢饉が五年から七年まで続き、
大塩平八郎の乱など百姓一揆や町民一揆起こる。崋山の推挙により大蔵永常が 田原藩士として迎えられた。
・天保六年(1835):崋山43歳のとき、崋山の献言により領民救済のための「報民倉」が建設される。
・天保七年(1836):崋山44歳のとき、7月・8月大暴風雨により田原壊滅。崋山激務のため病床に伏す。
・天保八年(1837):崋山45歳のとき、真木市郎兵衛定前(さだちか)を名代とし鈴木春山を同行させ派遣した。真木に託された崋山の『凶荒心得書』に は「抑君の職と申は、此民有て君有ㇾ之天理にて、此君ありて此民有ㇾ之節には無ㇾ之候」とあり、救済・復興は民・百姓を第一すべきことを説く。
特に非常時 は「御領中に罷在候数万人の内、たとえいかに賤敷小民たりとも、一人にても餓死流亡に及び候はば、人君の大罪にて候」とまで断じ、危急の場合には、家格や 身分にこだわらす役人を投入し、「報民倉」を開いて救助にあたるべきだと進言。
天保時代は海防問題でも大きく揺れ、幕府は諸藩に対し海防を命令するが、具体的な海防対策は幕藩体制に制限され各藩に任せざるを得ななかった。
3)蘭学へのめざめ
崋山は西洋絵画とくに陰影法や遠近法の技法を学ぶうち洋学への目が開かれていた。
・天保二年(1831):岸和田藩の蘭医小関三英(出羽の鶴岡生まれ、天保六年幕府天文方オランダ書籍和解御用拝命)を知る。
・天保三年(1832):蘭学者高野長英(奥州の水沢生まれ、シーボルトから直接指導受けた当代随一の洋学者)を知る。田原藩内年寄役末席に就任し海防事 務掛りとなった崋山は、村上定平や鈴木春山を抜擢して蘭学を研究させ、巣鴨の下屋敷に隠居中の三宅友信にも参加させ、友信に蘭学を購入させ、三英や長英に 翻訳させ世界情勢を学んだ。
・天保八年(1837):江川太郎左衛門(坦庵)と交わる。
坦庵は崋山の友人幡崎鼎(かなえ)に蘭学を学び、谷文晁を共に絵の師とする。また、剣も同門で 江戸随一の剣客齋藤弥九郎が師範。
同年六月アメリカ商船モリソン号が日本人漂流民を乗せて浦賀港沖に投錨し、これを浦賀奉行が砲撃するモリソン号事件起こる。崋山たちは、モリソン号には高名なアジア通の英国人モリソンの乗った英船であろうと考え、モリソンのような大人物の船の打ち払いは世界から避難される 蛮行であると恥じた。
・天保九年(1838):江戸参府のオランダ商館長ニーマンとの対談『鴃舌小記』『鴃舌或門』を書く。十月、モリソン号再渡来の噂に接し、崋山は『慎機論』を書き、幕府の外国船打ち払い令に反対した。十二月、幕府は鳥居耀蔵(幕府儒官林大学頭術斎の二男)と江川坦庵に江戸湾防備を固めるための沿岸測量と見分を命令した。
・天保十年(1839):江川坦庵は崋山に測量や報告書のことで助言を求め、崋山はこれに対し、数学者内田弥太郎をはじめ、測量術の名手や測量機器を送り込み、また三月には測量絵図に添付する報告書「西洋事情書」も書き送った。この報告書には、海防を考えるうえでの前提となるヨーロッパ諸国の国情や動きが詳細に記されていた。
⇒崋山のヨーロッパ認識の偉大さは、単に西洋諸国の科学技術を高く評価するのはなく、その土台となった科学的精神まで注目したことである。
・同年五月十四日:崋山は老中水野忠邦の命を受けた北町奉行大草能登守高好から出頭を命じられ、即日入獄させられた。長英は五月十八日に自首して投獄、三英は五月二十三日に自殺した。
→崋山らに対する罪科は幕府の中で勢力の巻き返しを図る鳥居耀三ら守旧派のデッチあげであった。
守旧派のねらいは、崋山の背後にいる革新派洋学グループを一掃することであった。これがいわゆる「蛮社の獄」である。
・同年五月十四日:在野の儒家松崎慊堂の水野忠邦への直書が効を奏し、死罪を免れ十二月十八日に在所蟄居の身で出獄を許された。
・天保十一年(1840):一月十三日に田原へ護送。二十日には田原城下に到着し、護送の任に当たった藩士松岡次郎(のちに、崋山の長女かつと結婚)の家に移され、二月十六日には大倉永常が住んでいた池の原御産物御用屋敷に移った。
⇒蟄居中は作品には、「異魚図」「海錯図」「千山万水図」『虫魚帖』「月下鳴機図」「干公高門図」「黄粱一炊図」などの大作がある。
・天保十二年(1841):蟄居中の崋山の経済的苦しさを救おうとし、弟子の福田半香が江戸の画会で崋山の絵を売ろうとしたことが幕府の咎めを受け、崋山 は自分が生きている事が藩主や家族の迷惑になると判断し、十月十一日に自刃した。崋山四十九歳であった。
2.渡辺崋山の藩政経営思想に対するKMとしての考察
江戸時代は北半球が寒冷化した小氷河期にあり日本は度々大飢饉に見舞われた。崋山が生きた江戸時代後期(18世紀後半〜19世紀前半)には享保大飢饉があった。
江戸時代後期には松平定信が寛政の改革を推進し、その後徳川家斉に引き継がれた。寛政の改革は、町人・百姓に厳しく、旗本・御家人を過剰に保護する政策を採り、民衆の離反を招き、19世紀に入ると急速な制度疲労による硬直化が目立ち始め、大塩平八郎の乱など町人・百姓を巻き込んだ一揆が頻発した。
その頃、欧米諸国は18世紀後半の産業革命により急速に近代化し、自らの産業のために資源と市場を求めて世界各地に植民地獲得のための進出を始めた。
崋山が田原藩江戸家老となった頃、外国船が日本近海へ出没する機会が多くなり、幕府は日本との外交ルートを模索する外国使節や外国船の接触に対し、文政八年(1825)には異国船打払令を実行するなど、鎖国政策の継続を行った。 家斉の死後、天保十二年(1841)、老中水野忠邦が幕府権力の強化のために「天保の改革」を実施し財政再建のための諸政策を試みたが、いずれも効果は薄く、特に上知令は幕府財政の安定と国防の充実との両方を狙う意欲的な政策であったが、社会各層からの猛反対を浴びて頓挫し、忠邦もわずか3年で失脚した。
こうした中、薩摩藩や長州藩など有力藩では財政改革に成功し、幕末期の政局で強い発言力を持つことになった。
1)崋山の藩政政策と経営思想について
崋山は藩政として、天保四年(1833)に天候異変のため田原視察を行い洋式兵学者鈴木春山を同行した。
同年七月田原領内で発生した紀州商船遭難補償問題を少額賠償金で落着。
同時期、幕府からの新田開発の命の廃案に成功。同年十二月藩政の改革のため新俸禄体系「格高分合制」を導入した。
さらに、天保六年(1835)には崋山の献言により領民救済のための「報民倉」が建設され、
天保七年(1836)には7月・8月大暴風雨により田原壊滅し、崋山は激務のため病床に伏した。
このように藩政では、救済・復興は民・百姓を第一すべきことを説き、危急の場合には、家格や身分にこだわらす役人を投入し救助にあたるべきだと進言し「報民倉」を建設し、民・百姓の求心に成功した。
当時、地方の小藩である田原藩の産業は農業が中心であり、その点で現在とは産業構造が異なるが、崋山の藩政政策は民・百姓を第一にした政策を取っており、その意味では現在のマーケティング志向に通じる顧客満足・従業員満足の政策といえる。
2)崋山の海外戦略について
一方で、天保三年(1832)田原藩内年寄役末席に就任し海防事務掛りとなった崋山は、村上定平や鈴木春山を抜擢して蘭学を研究させ、巣鴨の下屋敷に隠居中の三宅友信にも参加させ、友信に蘭学を購入させ、三英や長英に翻訳させ世界情勢を学んだ。
天保八年(1837)六月にアメリカ商船モリソン号が日本人漂民を乗せて浦賀港沖に投錨し、これを浦賀奉行が砲撃するモリソン号事件が起こった。
崋山たちは、モリソン号には高名なアジア通の英国人モリソンの乗った英船であろうと考え、モリソンのような大人物の船の打ち払いは世界から避難される蛮行であると恥じた。
天保九年(1838)十月、モリソン号再渡来の噂に接し、崋山は『慎機論』を書き、幕府の外国船打ち払い令に反対した。同年十二月、幕府は鳥居耀蔵(幕府儒官林大学頭術斎の二男)と江川坦庵に江戸湾防備を固めるための沿岸測量と見分を命令した。崋山は江川坦庵からの協力要請に対し、数学者内田弥太郎をはじめ、測量術の名手や測量機器を送り込み、また翌年
三月には測量絵図に添付する報告書「西洋事情書」も書き送った。
この『慎機論』や「西洋事情書」では、世界の現状からみて、わが国のみが鎖国体制を維持しようとしても、それは不可能なばかりか、かえって敵に侵略の口実を与えることになるとし、最後に激しい口調で為政者の無能を批判した文案を書きためていた事が発覚し「蛮社の獄」で有罪となった。
このように、崋山は田原藩海防事務掛りとして、日本海域に渡来する外国船への防備のために海外事情を収集し、『慎機論』や「西洋事情書」を起稿し、幕府への進言の機会を待っていたが、逆にこれを幕府の中で勢力の巻き返しを図る旧守派の老中水野忠邦や鳥居耀蔵の策略に利用されてしまった。
グローバル経済時代となった今日、海外事情は企業業績にダイレクトな影響を与えるため、そのタイムリーな入手・分析は企業継続上の重要課題である。
鎖国時代という限定された条件のもと、世界事情を学ぶ仕組みの構築と人材の獲得により、単に西洋諸国の科学技術を高く評価するのはなく、その土台となった科学的精神までをも注目し「世界の現状からみて、わが国のみが鎖国体制を維持しようとしても、それは不可能なばかりか、かえって敵に侵略の口実を与えることになる」との結論に至った高度な分析眼は賞賛に値する。
3)崋山の思想とKMについて
崋山が生きた江戸時代の末期は、徳川幕府による統治制度が綻び始め、また欧米諸国では蒸気機関の発明など科学技術が目覚ましく発展した時代でもあり、これら最新技術を搭載した黒船が日本に度々押し寄せ開国を迫るなど環境変化が著しい時代でもあった。
崋山の思想は代々田原藩主に使える家臣としての「忠義」と老母に対する「忠孝」という儒学思想が基盤となっている。しかし、渡辺家の家計を補うため絵画を描き続けた事から西洋絵画の陰影法や遠近法の技法などを学び、そして、蘭学を通じて西洋の科学技術を学ぶ中で西洋の科学的精神の先進性を知り、鎖国撤廃つまり開国論に至った。ただし、崋山は天皇に触れることは一切なかった。
崋山の思想をKMの視点でみると、ナレッジ交流の場づくりでは、鎖国政策という逆風の中でも熱心な蘭学研究を重ね、蘭学研究の場を構築するばかりでな
く、儒学思想家の場にも参加し自由闊達に意見を述べるなど、単に武士の視点だけではなく芸術家としての視点、つまり複眼的視点で物事を考えることが出来た
と見るべきであろう。
この複眼的視点は、今日の企業経営に関わるステークフォルダの視点で経営を見直すことにも通じる視点である。また、グローバル経営時代におけるKMの視
点として、海外との比較文化的思考の重要性を示唆しているともいえよう。
(文責:小野瀬由一)
Back number
■第一回議事録
■第二回議事録
■第三回議事録
■第四回議事録
■第五回議事録
■第六回議事録
■第七回議事録
■第八回議事録
■第九回議事録
■第十回議事録
■第十一回議事録
■第十二回議事録
■第十三回議事録
■第十四回議事録
■第十五回議事録
■第十六回議事録
■第十七回議事録
■第十八回議事録
■第十九回議事録
■第二十回議事録
■第二十一回議事録
■第二十二回議事録
■第二十三回議事録
■第二十四回議事録
■第二十五回議事録
■第二十六回議事録
■第二十七回議事録
■第二十八回議事録
Copyright © TKF2012. All rights reserved.